【アグリ・バイオ・ロボティクス・ドローン】Deep Techスタートアップ起業プログラム「NEXUS:S」と技術シーズのご紹介 - 北海道共創パートナーズ x upto4
upto4は、スタートアップに関心のある方が、創業初期スタートアップ創業者やベンチャーキャピタル、創業を予定する技術シーズ保有研究者と気軽な情報交換や週2-3時間からスタートアップに参加できるコミュニティを作っています。
今回、北海道発ユニコーン企業創出を目指すDeep Techスタートアップ起業プログラム「NEXUS:S」の取り組みの一環として、北海道共創パートナーズ(以下、HKP)とupto4による起業イベントを開催いたします。
■イベント詳細
起業プログラム「NEXUS:S」のご紹介と、プログラムに参加されている【アグリ・バイオ・ロボティクス・ドローン分野】で創業を目指しCEO候補を求めている研究者6名から研究内容をご紹介いただきます。
大学の技術シーズを活かした創業期スタートアップへの参画に興味を持つ方にとって、世界を変える一歩を踏み出すセッションとなっております。
Q&Aセッションは匿名ツールを使用しておりますので、聞きづらいこともお気軽にご質問ください!
・NEXUS:Sとは
北海道発のDeep Techスタートアップとして起業を目指すプログラムです。 HKPがこれまで培ってきたノウハウを活用し、社会実装によって社会課題の解決を目指すCEO候補者と北海道の大学等の優れた研究成果との出会いをサポートします。 研究者とマッチングされたCEO候補者の方には、8ヶ月間のインキュベーションプログラムに参画いただきます。大学発等ディープテックスタートアップ創出の経験が豊富なメンターが丁寧に伴走し、事業化支援や資金調達機会の提供も行います。
※ご応募多数の場合は選考となります。予めご了承ください。
※本イベントは、プログラムに参加している一部のシーズのみのご紹介です。
ーーーーーーーーーー
今回ご紹介するシーズ技術
・【アグリ】マルチAIカメラを使用したワイン用ブドウの収穫ロボットの開発
北見工業大学 工学部 准教授 楊 亮亮 先生
近年各地でワイナリーの数が増えている。ブドウを収穫するための作業員の確保が難しいのが現状である。ワイン用ブドウの収穫を自動化するため、マルチAIカメラを使用した収穫ロボットを開発した。ワイナリーの経営法人をターゲットと想定し、収穫ロボットを販売する。年間2000台の販売と想定している。収穫ロボットは収穫時に、糖度の高いものだけを収穫できるメリットがあるため、高品質のワインを製造することができる。加えて、収穫時のブドウの写真データを保存できるため、ロボットを長年使用することによりブドウの成長記録が追跡可能となる。今後このデータを消費者に共用することができれば、消費者に対して日本ワインを飲む安心感を与えることができる。
・【アグリ】リモートセンシング×AI=牧草地の健康診断ツールを開発する
帯広畜産大学 環境農学研究部門 准教授 川村 健介 先生
リモートセンシング技術(ドローン・人工衛星)とAIを活用し、牧草地の生育状況や雑草分布をスマートフォンなどで簡単に確認できる「見える化」サービスを展開します。本システムでは、従来の営農支援では難しかった牧草地の詳細な生育情報や植生データ(マメ科率・雑草分布)を提供します。これにより、生産者や農協は草地更新の判断や施肥・収穫時期の最適化が可能となり、収量および品質向上を支援します。
・【アグリ】植物の健康状態を可視化するスマート農業用デバイスの開発
北海道情報大学 経営情報学部システム情報学科 教授 栗原 純一 先生
農業生産者向けに農作物をはじめとする植物の健康状態を可視化するスマート農業用デバイスの製品化を目指す。最初の顧客候補は日本国内のリンゴ生産者で、市場規模は生産額ベースで1547億円である。国内のほぼすべてのリンゴ生産者が「リンゴ腐らん病」というリンゴ樹の病害に悩まされており、この病気が原因で廃業に追い込まれる生産者も多い。この病気は早期発見が重要だが、目視での検出が難しく、有効な防除剤もない。現在開発中のスマート農業用デバイスを用いることで、この病気を簡単に可視化することができる。将来的にはほかの農作物にも応用が可能である。
・【バイオ】産業用バイオナノファイバー生産プロセスおよび繊維材料の開発・製造
北海道大学 工学研究院 博士研究員 高濱 良 氏
北海道の特産品である甜菜に由来する糖蜜を出発物として、微生物変換と紡糸技術を駆使したセルロース長繊維の生産プロセスを開発、各ステップのライセンスおよび自己実施による事業化に取り組む。本製品は従来の樹脂補強繊維であるガラス繊維や炭素繊維と比較し低エネルギーで生産でき、軽量性や低膨張率といった優れた物性も有する。繊維化することで既存の樹脂加工設備と販売ルートを通した自動車部品等の市場への展開を目指す。
・【ロボティクス】力触覚を有する誰でも作業教示可能な汎用ロボットと水産業の改革
北海道大学 工学院 博士1年 牧 駿 氏
世界における労働人口の減少が顕著になっている。世界で様々なロボットによる対抗策が打ち出されているが致命的な課題が2点存在する。「力の扱い方」という概念の欠如と、自動化する際に多大なリソースが必要となることである。これに対し本プロジェクトはロボットと操作者の手先の感覚と動きを完全シンクロさせることで直感的に操作し、自動化したい作業を5分で教えられるロボットを水産加工業界に提供する。人手不足が産業全般の中でも特に深刻であり自動化も進んでいないためである。
・【ドローン】観光x災害対応ドローンシステムの研究および事業開発
公立はこだて未来大学 システム情報科学部 准教授 西沢 俊広 先生
観光と災害対応のハイブリット運用が可能なドローンシステムの研究を推進している。平常時に観光地において記念撮影サービスを提供し、災害発生時には災害状況把握のために運用する。北海道には多くの風光明媚な観光地が存在するが、一方で活火山が多く噴火災害の危機に対峙している。我々は自動飛行制御技術、自動動画編集技術、災害調査画像技術の開発を進めている。習熟した機体操縦技能や動画編集技能が不要で、記念撮影や災害状況把握が可能なシステムの事業化を目指す。
ーーーーーーーーーー
・本イベントのポイント
- 北海道発ユニコーン企業創出を目指す、Deep Techスタートアップ起業プログラム「NEXUS:S」の詳細がわかる
- CEO候補としてインキュベーションプログラムへの参画に興味がある方は、後日カジュアル面談
・イベントの背景、目的
大学の研究成果を社会に還元することを目指しています。
・北海道共創パートナーズ(HKP)とは
HKPは、北洋銀行が持つ、あらゆる業種・業態の道内企業との強固な顧客接点をバックボーンに事業を展開する北洋銀行100%出資の子会社です。北洋銀行取引先企業の経営者様と直接対話を行い、様々な経営課題を解決すべく、経営コンサルティング、経営人材紹介、事業承継、補助金申請等の伴走支援を実践しています。
・ご注意事項
本イベントは参加者様の顔が映らない状態で録画し、広報等に使用させていただきます。
■タイムライン
2025年1月21日(火)
19:00-19:05 イベント説明、upto4のご紹介
19:05-19:10 HKPとNEXUS:Sのご紹介
19:10-19:15 匿名質問ツールSlidoの操作方法
19:15-20:29 【アグリ】楊先生よりシーズ技術のご紹介とQ&A
19:29-19:43 【アグリ】川村先生よりシーズ技術のご紹介とQ&A
19:43-19:57 【アグリ】栗原先生よりシーズ技術のご紹介とQ&A
19:57-20:11 【バイオ】高濱先生よりシーズ技術のご紹介とQ&A
20:11-20:25 【ロボティクス】牧先生よりシーズ技術のご紹介とQ&A
20:25-20:39 【ドローン】西沢先生よりシーズ技術のご紹介とQ&A
20:39-20:45 NEXUS:Sへのエントリー方法について
※途中入退場自由です、ご関心のある先生の時間帯のみのご参加も大歓迎です。
※多少進行が前後する可能性がございます
■登壇者

楊 亮亮|Liangliang YANG
北見工業大学 工学部 准教授
大学時代に、中国の世界トップレベルの農業大学で農業機械と情報工学のダブルディグリーを取得し、その後、電気工学の修士号を取得しました。2009年に来日し、北海道大学でRTK-GNSSを用いた農業用ロボットトラクターの研究に従事しました。現在は、文部科学省、内閣府、農林水産省の事業に携わり、農業用移動ロボットやAIカメラを活用した収穫ロボットの研究開発を行っています。

川村 健介|Kensuke Kawamura
帯広畜産大学 環境農学研究部門 准教授
リモートセンシングとIT技術を活用し、草地生態学および放牧管理技術を研究。草地診断や飼料成分評価を通じ、スマート農業に貢献。ポスドク時代は、ニュージーランドで放牧管理の研究に携わる。ラオスやマダガスカルでは持続的な米生産の迅速評価技術にも取り組む。専門分野は草地学、植物生態学、リモートセンシング。博士(農学、岐阜大学、2005年)取得。

栗原 純一|Junichi Kurihara
北海道情報大学 経営情報学部システム情報学科 教授
2004年に東京大学にて博士(理学)取得後、JAXA宇宙科学研究本部、名古屋大学太陽地球環境研究所、北海道大学大学院理学研究院を経て、2022年より北海道情報大学・准教授、2024年より同教授となる。専門分野は宇宙惑星科学、航空宇宙工学、農業情報工学等。特に人工衛星やドローンからのマルチ・ハイパースペクトルリモートセンシングを用いた、持続可能な世界への貢献をテーマとした研究を行っている。

高濱 良 |Ryo Takahama
北海道大学 工学研究院 博士研究員
九州大学にて博士(農学)取得後、2022年度より現職。田島健次准教授のもとでセルロースをはじめ多糖類の微生物合成と産業応用に関する研究に取り組んでいる。主なテーマはセルロース合成菌である酢酸菌の分子育種と培養技術開発。現在フランス国立科学研究センター植物高分子研究所(CERMAV)客員研究員としてキチンおよびヒアルロン酸の微生物合成に関する研究にトライしている(2025年3月まで)。趣味は釣りハイキング料理ヨット。

牧 駿|Shun Maki
北海道大学 工学院 博士1年
ロボティクス、AI、生体機械工学を融合することで従来ロボットの柔軟性の欠如を解決し人でないと出来ない作業、仕事をなくすことを目指している。これまで数多くの手先の感覚とロボットにまつわる開発系プロジェクトを牽引し開発スキルを身につけると共に仲間を増やしてきた。現在は北海道大学の学生として共同研究先である慶應義塾大学にて客員研究員として研究開発活動を実施している。

西沢 俊広| Toshihiro Nishizawa
公立はこだて未来大学 システム情報科学部 准教授
NECにてパーソナルロボットの研究開発を担当した後、宇宙ステーション補給機こうのとりの誘導センサの開発に従事。その後、インフラ点検ドローン、ドローン運航管理システムの研究と事業開発を担当。独立行政法人情報処理推進機構出向時にはドローン利活用社会のアーキテクチャ設計を担当し、ドローンの政策検討を支援した。2024年4月にはこだて未来大に着任し、地域社会の課題解決ができるロボット・ドローンの研究開発・教育を推進。2012年筑波大学にて博士(工学)を取得。

酒向 厚輔|Kosuke Sako
株式会社北海道共創パートナーズ 人材事業部コンサルタント
同志社大学政策学部卒業後、人材サービス企業のパーソルを経て、2022年に北海道共創パートナーズへキャリアアドバイザーとして入社。これまで北海道でのハイクラス転職支援で200名以上を支援。現在は道内スタートアップ、ベンチャー企業への人材紹介や本プログラム「NEXUS:S」を推進。 ”北海道で事を成したいエネルギー溢れる人材と未来を担うスタートアップとのマッチングにより北海道をより魅力的な場所にする”をモットーに日々奮闘中。国家資格キャリアコンサルタント保有。

棟兼 彰一|Shoichi Munekane
upto4株式会社 代表取締役
早稲田大学政治経済学部卒 システムコンサルタントを経て、大手人材会社にて事業企画、ベンチャー投資、M&Aなどを担当。
大学発創薬スタートアップ、ヘルスケアスタートアップでコーポレート・新規事業開発などを経てupto4を創業。
■本イベントの申込
こちらからお申込みください。
■当日の流れ
当日はzoomで開催します。
peatixにご登録のメールアドレス宛に参加リンクをお送りします。
■イベント後の流れ
「NEXUS:S」や今回ご紹介する先生方の事業化支援にご興味をお持ちいただけた方には、イベント終了後、応募方法をご案内いたします。
■主催
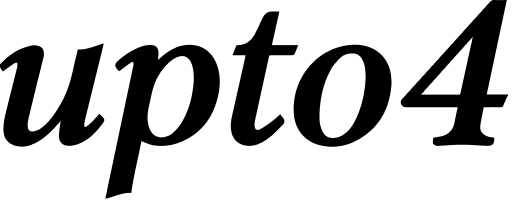
upto4株式会社
「世界を変えるような機会を、あなたに。」
upto4は、創業前・創業期のスタートアップ経営者やベンチャーキャピタルと情報交換ができる審査制コミュニティです。
創業前〜創業4年目までのスタートアップが74%を占めます。
創業者とのオンラインピッチデックミーティングをきっかけに、あなたの空いている時間で、世界を変えるかもしれない事業や研究開発に将来の社長・取締役・CxOとして参画できる場をつくっています。
https://www.upto4.com (メンバー登録はこちら / 審査制となります)
■事務局からのお知らせ
内容は一部変更になる場合がございます。
オンラインですので全国どこからでもお気軽にご参加ください。
■イベントに関するお問い合わせ
upto4株式会社
X(旧Twitter):@upto4_com(お気軽にDMください!)
メール:alice.narumiya@upto4.com(成宮)
2025-01-16